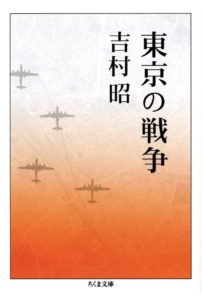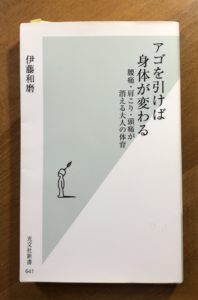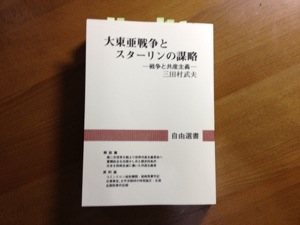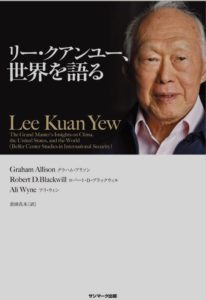
kindle版を購入し、面白かったので二回読みました。
シンガポールを今日のように発展させたリークアンユーさんが今後の世界情勢について語っておられます。
たいへん説得力のある内容で、興味深い。
アメリカの未来
・アメリカ経済が傑出しているのは、起業家精神が社会に根付いているからだ。
・起業家も投資家もリスクや失敗を成功につきものの不可欠な要素だとみなす。
・アメリカで成功している企業はみな、何度も挑戦しては失敗している。
・アメリカ起業文化の特色 ①国が個人の自立と独立独歩を重視すること②新規事業を始めた者を尊重すること③企業や革新の努力が失敗しても受け入れること④大きな所得格差を容認すること
・アメリカは債務超過や赤字に悩まされているが、だからといって二流国家に転落することはない。歴史を振り返るとアメリカは革新や再生の能力が高いことがわかる。
・アメリカ社会は歴史も文化も宗教も異なる相手を、簡単に仲間として受け入れる
・きわめて危険なのは、アメリカ経済の回復に時間がかかりすぎてアメリカが保護主義的になり、貿易摩擦や日本バッシングが拡大することだ。最悪の場合には貿易や経済の関係が悪化し、相互の安全保障関係が弱体化し、破綻してしまう。
日本についてはあまり書かれていませんが、日本はアメリカの逆(起業や革新の精神に欠ける、閉鎖的、保護主義的など)の性格をもつ国なので、暗に今後は衰退するといっておられるように私は感じます。
日本がアメリカのような起業社会・資本主義社会になれるかというと、これは絶対に無理なので、今迄通り保護主義・社会主義的な社会であり続けるしかないのですが、今までと違って今後は、そのことが日米関係を悪化させるようになる。
そうすると本当に「きわめて危険な」状況が起こるかもしれません。
インドの未来、中国の未来、イスラム原理主義の未来など、日米以外の国々のことも詳しく書かれています。